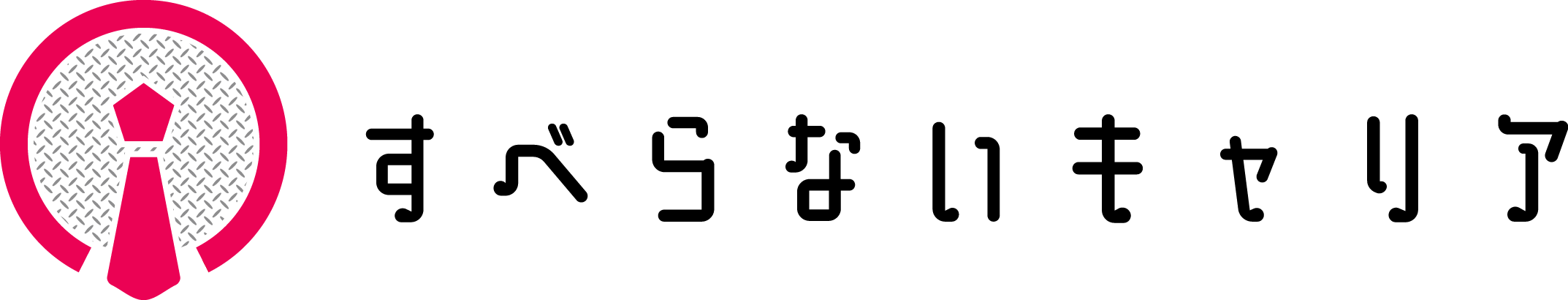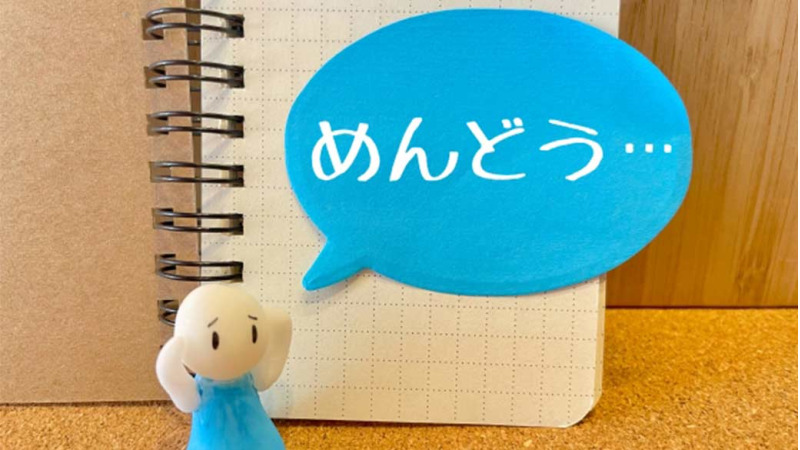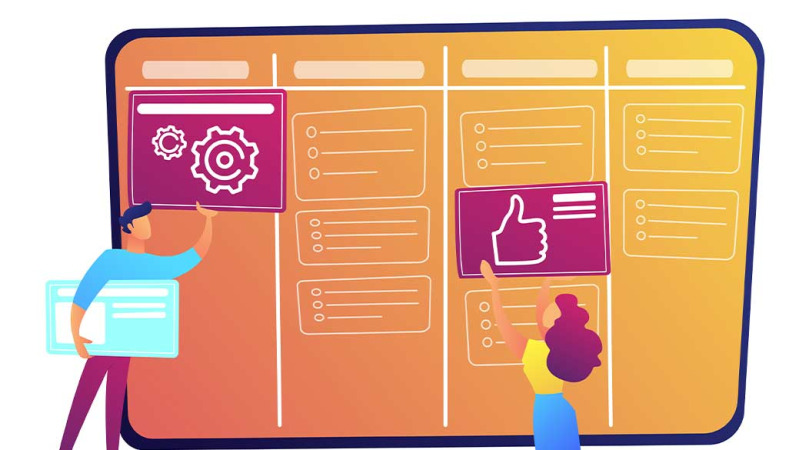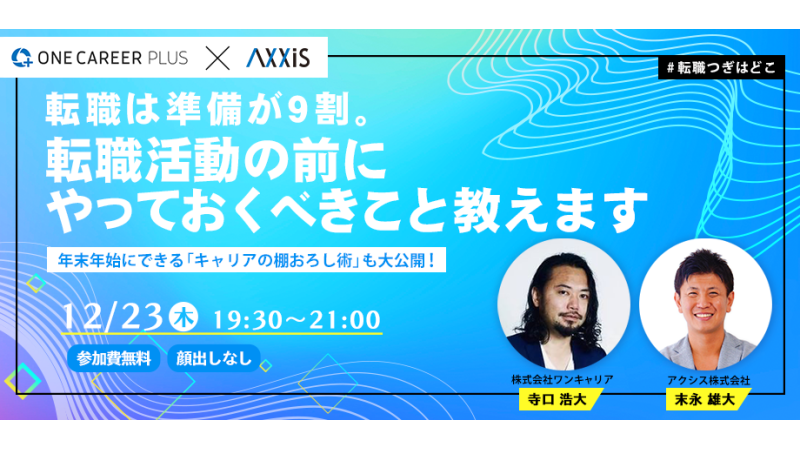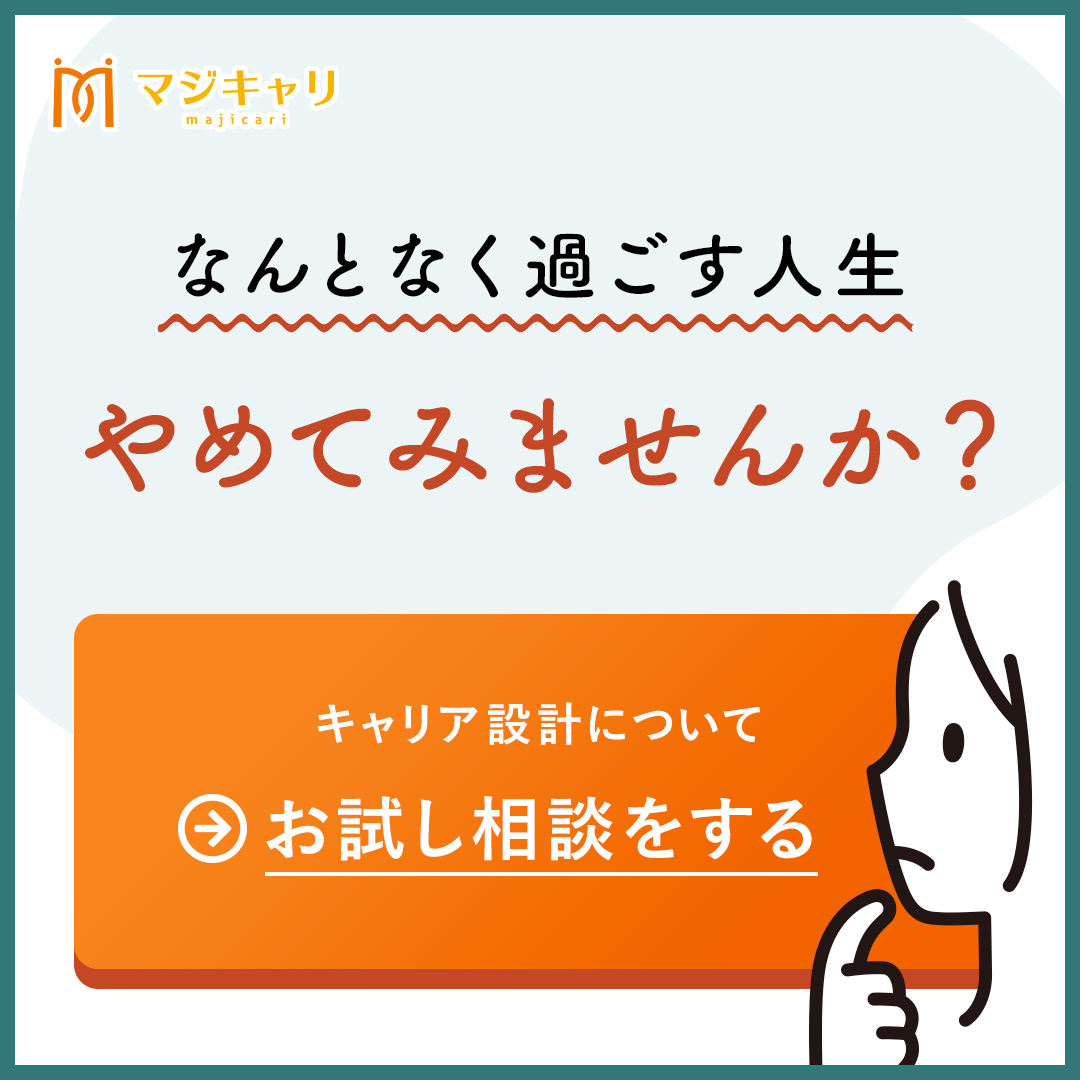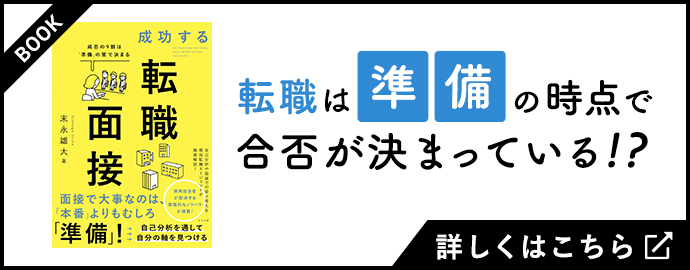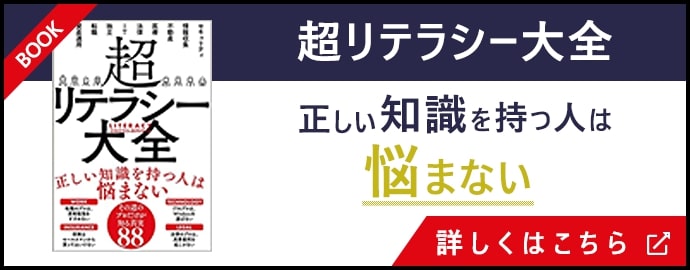目次
昨今では、ビジネスシーンでダイバーシティ・マネジメントが主流になりつつあり、多種多様な人々の意見をまとめ、価値観を共有する重要性が高まっています。
その中でもファシリテーションは会議や研修において、参加者の考え方を尊重し、意見交換を促していくために必要とされており、ビジネスシーンにおいて活用されることが多くなってきました。
しかし、
「ファシリテーションを行うためには何を意識すれば良いのかわからない」
「なにをもってファシリテーションができていると判断すれば良いのかわからない」
という人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、ファシリテーションの意味や目的、必要なスキルなどについて詳しく紹介してきます。
本記事を読むことで、ファシリテーションにおいて必要なポイントを知り、ファシリテーターとして組織をマネジメントすることが可能になるでしょう。
ファシリテーションとは?
ファシリテーションとは、複数人が集まり話し合う場において、メンバーの発言を促したり、話を整理して理解を促したりと、話し合いにおける支援をおこなっていくことです。
また、ビジネスシーンにおいては会議やミーティング、もしくは研修などの場面で活用されており、ファシリテーションをおこなう人のことを「ファシリテーター」と呼びます。
話し合いの場でファシリテーターが上手く進行していくことができれば、
- 話し合いで意見が出ずに時間だけが過ぎていく
- 話し合っても要点がまとまらず時間内に話し合いが終わらない
このような話し合いにおける問題点を解消し、スムーズに意見交換をしていくことができるようになるため、ファシリテーターは重要な役割を担っています。
ファシリテーションの目的
ファシリテーションの目的は、参加者の意見を取り入れつつ、スムーズに目標達成していくことです。
そのため、ファシリテーターは議題に対する参加者の発言を促し、それぞれの意見をまとめる必要があります。
とくに、会議などの話し合いの場では、考え方が異なる人が集まることが多く、調整役は必要不可欠です。
ファシリテーターは、参加者の考えを汲み取り、意見を整理して取りまとめ、議題に対する結果の合意形成までおこないます。
ファシリテーターが機能することで、会議の質を高めることにつながり、結果として議題に対する結論が明確になるため、会議においてファシリテーターは欠かせない存在といえるでしょう。
ファシリテーションが注目されている理由
近年、とくにビジネスの現場において、ファシリテーションが注目されています。
その理由として挙げられるのが以下の通りです。
- 会議などに参加する人全員が納得したうえで合意形成ができる
- 議題に関する新しいアイデアが出る可能性もある
- 参加者のモチベーションを向上させることができる
- 異なる文化や言語を持つ参加者同士でも意思疎通を行いやすい
ファシリテーションには上記のようなメリットがあり、会議などの話し合いの場をスムーズに進めていくために有効だと認識されています。
また、ファシリテーションを取り入れることで、会議で起こりうる「議題の結論が決まらず時間がかかってしまう」「話し合いに参加する人が少なく偏った意見しか集まらない」というような課題を解決するために活用することも可能です。
そして、ファシリテーションは上手く活用することで、参加者全員の発言を促し、全体の意見をまとめることができるため、明確な結論を出しやすくなります。
その結果、会議後の明確な行動指標が決まり、よりスムーズに業務に取り組むことができるようになるでしょう。
ファシリテーターの役割
ここまで、ファシリテーションについて詳しく解説してきましたが、具体的にファシリテーターはどのような役割をこなす必要があるのでしょうか?
ファシリテーターは司会進行だけではなく、以下のような役割も求められています。
それぞれの役割について以下で詳しくお伝えしていきます。
ミーティングなどのゴールの設定
ファシリテーターの役割の中でも、ゴールの設定は最も重要な役割です。
会議などの話し合いの場において、ゴール明確にしておかなければ、「話の焦点が定まらずに検討違いな結論を出してしまう」「議題の結論が出ずに時間だけが過ぎていく」というような、話し合いの質の低下を招きます。
そのため、ファシリテーターとして会議を進める時には、会議のはじめに参加者全員と以下の2つの情報共有をおこないましょう。
- 会議のテーマと目的
- 会議の明確なゴール
会議において「何をテーマ(議題)としているのか」「どのような目的で話し合うのか」は大切なポイントです。
そして、ゴールは、「今回の会議で何をすれば目標(ゴール)が達成されるのか」という視点で考えて共有すると良いでしょう。
また、テーマ・目的・ゴールは会議中に常に目に入る場所に書き出しておくと、意見出しや情報の整理をする時にも、立ち返って考えることができるのでオススメです。
発言しやすい雰囲気作り
参加者にとって発言しやすい環境を整えてあげることも、ファシリテーターの重要な役割の一つです。
会議において、特定の人物だけの意見が強く反映されてしまうことは避けなければいけません。
そのため、ファシリテーターは会議を進めるにあたり、「全体の意見に偏りがないかどうか」「発言が少ない人はどのような考えを持っているのか」を意識して、進行していくと良いでしょう。
会議において、発言しやすい雰囲気作りができていれば、多くの意見を聞いて判断することができます。
その結果、思いも寄らないアイデアが出てきたり、チームのコミュニケーションが活発になったりとさまざまな効果が期待できるでしょう。
また、発言しやすい雰囲気を作るためには、「意見を批判しないこと」「中立的な立場で話を聞くこと」が大切なポイントになります。
批判せずに意見交換をしていくために有効な手段として、ブレインストーミングの考え方が参考になるので、併せて参考にしてみてください。
タイムマネジメント
ファシリテーターとして会議を適切に進めていく場合には、タイムマネジメントも大切です。
話し合いの場において、「意見を出し合っていると気がつけば時間が経ってしまっている」ということはよくありますが、長時間の会議は質の低下を招きます。
また、本来やるべき業務にも影響が出る可能性もあります。
そのため、話し合いや意見出しにも時間を明確に区切り、会議を時間通りに終わらせるために適切な時間管理を行っていくようにしましょう。
また、適切なタイムマネジメントをするためには、事前にアジェンダの共有をしておくことが有効です。
アジェンダを共有しておくことで、参加者全員が会議の全体像を把握することができ、議題の優先順位付けもしやすくなるからです。
その結果、会議において優先順位の低い項目の話が長びいた時には、途中で切り上げて優先度の高い話に時間を割くなど、適切なタイムマネジメントがやりやすくなります。
意見の整理
適切な雰囲気作りやタイムマネジメントができるようになると、会議中の意見も増えます。
しかし、参加者が出した意見を取りまとめて、話し合いの方向性を明確にする人がいなければ、結論を出せずに会議が終わってしまうこともあるでしょう。
そのため、ファシリテーターは参加者の意見を促すとともに、出てきた意見を整理して取りまとめる必要があります。
また、ファシリテータが話を整理する際には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- 意見の要点を明確にする
- 意見のカテゴリを分けて整理する
- すぐに共有できるようにホワイトボードなどに書き出す
これらのポイントは、情報をまとめるとともに情報を可視化することで理解を促し、更なる意見を出していくためにも有効です。
また、可視化しておくことで話し合いの論点がずれていないか確認することもできるため、効率的に会議を進めることにもつながるでしょう。
参加者のコンセンサスを得る
参加者のコンセンサスを得ることもファシリテーターの重要な役割です。
コンセンサスとは、『参加者それぞれの合意や意見の一致』という意味があり、ファシリテーターは不満が出ない形で会議やミーティングを収束させる必要があります。
しかし、実際の会議では結論に対して全員の同意を得ることが難しいケースもあるでしょう。
そのような場合には、反対している人の主張を改めて聞き直し、その主張を聞いた上で議論を深めていくことが大切です。
また、反対意見が現時点で優先すべき内容ではなかった場合には、「Aさんにとって○○することは難しいかと思うが、△△の部分を削ってみてはどうだろう」というように、ファシリテーターとして中立の立場で自らアイデアを出してみるの良いでしょう。
ファシリテーションが上手な人の特徴
ここまでファシリテーターの役割を5つのポイントに分けてお伝えしました。
では、ファシリテーションが上手な人とは、一体どのような人を指すのでしょうか。
ファシリテーションが上手な人の特徴は以下の通りです。
それぞれについて、解説していきます。
あらゆる意見に対して関心を持てる
参加者のあらゆる意見に対してファシリテーター自身が興味・関心を持つことは、話し合いにおいて発言しやすい雰囲気作りへとつながります。
また、ファシリテーションが上手な人は、「気になる点があれば話を深掘りをする」「話を要約して参加者が理解しやすいようにする」という点を意識している人も多いです。
どのような場面でも、人は自分の話に耳を傾けようとしない人には意見を出そうとは思いません。
だからこそ、ファシリテーターが率先して意見に耳を傾けることで、参加者は意見を出しやすくなり、多くの意見交換ができるようになるのです。
目的を意識しながら論点を見極めることができる
目的を意識しながら論点を見極めることができるというのも、ファシリテーションが上手な人の特徴として挙げられます。
会議を進めていく中で、積極的な意見交換ができるようになると、話が議題から外れたり、論点がずれてしまうこともあるでしょう。
しかし、ファシリテーションが上手な人は、常に話し合いにおける目的を意識できているため、適時修正しながら、目的に向けて話し合いを進めることができています。
結果として、ファシリテーションが上手な人がファシリテーターをおこなうことで、無駄なく話し合いを進め、適切な会議進行することにつながるのです。
常に全員の様子に目を配ることができる
常に参加者全員の様子に目を配ることは、会議やミーティングをスムーズに進めるためには欠かせません。
たとえば結論に納得できない人がいると、会議の最後に反対意見を出して議論が長引いてしまう恐れもあります。
しかし、ファシリテーションを上手におこなえる人は、会議中はいつでも参加者を観察し、本当に納得できているかどうかを確認したうえで会議を進めることを意識しています。
そのため、疑念や不服が少しでも表情や態度に現れるようであれば、その人の意見を聞いてコンセンサスを得ようとするでしょう。
結果として、参加者の同意の上で議論を進めることができるため、効率的に会議をおこなうことができるのです。
ファシリテーションに必要なスキル
ここからはファシリテーションをおこなう際に重要なコミュニケーションに関連するスキルについて紹介していきます。
具体的には、以下のスキルが重要になってきます。
それぞれについて解説していきます。
傾聴力
「傾聴力」は、ファシリテーションをおこなうにあたって重要なスキルの一つです。
傾聴することで、「話しやすい雰囲気を作ることができる」「話を深掘りして本質を明らかにすることにつながる」というメリットがあるからです。
また、傾聴する際に意識べきポイントが3つあります。
- 相手の意見に対して相槌を打つ
- 必要に応じて質問を行い掘り下げる
- 相手の意見に対して相槌を打つ
傾聴は、ファシリテーションだけではなく様々なビジネスシーンで活用することができます。
なので、今回紹介した3つのポイントを意識しながら、積極的に傾聴するようにしましょう。
要約力
会議を進めてく際に、意見を整理してまとめるための「要約力』もファシリテーターにとって必要なスキルの一つです。
要約する際には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- 意見のポイントを整理して全体にわかりやすいように端的にまとめる
- 専門的な言葉があればわかりやすい言葉に変換する
話の要約をおこなうことで、意見を出してくれた人も「内容を理解してもらえた」と安心して、より積極的に意見を出してくれるようになります。
また、全体の意見の方向性を確認することにもつながるため、目的からそれていないか、意見に偏りがないかなど話し合いの全体像を俯瞰的に見ることがにもつながるでしょう。
調整力
「調整力」もファシリテーションにおいて重要なスキルの一つです。
調整力と聞くとイメージしにくいかもしれませんが、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 参加者全体のバランスを見て意見が少ない人に話を振る
- 意見に偏りがある場合には別の視点から意見を出して話の展開を広げる
- 似たような意見があれば、カテゴリに分けて整理する
これらは中立の立場としてファシリテーションをしていくにあたり必要です。
また、調整が上手くできることでより良い意見が生まれたり、結論を出す際に判断しやすくなったりするため、ファシリテーターとして調整力は意識して磨いていくと良いでしょう。
ファシリテーションを成功に導くポイント
ファシリテーションが上手く作用するようになると、「いつもムダな会議ばかり…」とため息をつくこともなくなります。
それどころか参加者全員が会議を開く意義を理解でき、会社にとって有用な時間を皆で共有することができるでしょう。
そのためにも、以下でお伝えするファシリテーションを成功に導くポイントを学んでいきましょう。
それぞれについて解説していきます。
事前準備は入念におこなう
会議を円滑に進めてファシリテーションを成功に導くためには、事前準備を入念におこなうことが重要です。
会議におけるアジェンダや目的・ゴールの設定、必要な資料集めや情報共有などは、自分だけではなく参加者にも事前に準備をしてもらうことで、会議を効率的に進めることができます。
また、効率的で質の高い会議をおこなうためには、あらかじめ「1時間以上は会議をしない」「議題に対してアイデアを事前に考えておく」などの会議のルールを明確にしておくのもオススメです。
意見は端的に伝える
参加者の意見を尊重することは大切ですが、意見を出す場合は要点を端的にまとめて伝えることを意識しましょう。
会議において時間が長くなる要因は、意見の要点をまとめずに長々と話をしてしまうことです。
そのため、意見を伝える際には端的に話をすることを心がけ、参加者の意見が長く要点が掴めない場合には、ファシリテーターが意見を要約するなど、工夫をしていくと良いでしょう。
質問を深堀りして議論をふくらませる
会議を進めていく上で、意見が少なかったり偏りがある場合には、ファシリテーターが議論に対して質問を投げかけ、話を広げていく必要があります。
また、質問を投げかける際には「Yes」「No」で答えられる「クローズクエスチョン」ではなく、「How(どのように思うか)」で答える必要がある「オープンクエスチョン」で質問をするようにしましょう。
わかりにくい意見は要約する
会議やミーティングに参加する人のすべてが話し上手とは限りません。
むしろ、「どちらかといえば自分は話し下手」と答える人のほうが多いでしょう。
そこで、意見がわかりづらいと感じた場合、ファシリテーターが噛み砕いて説明してあげることが大切です。
そのためには、ただ相手の話を黙って聞くのではなく、相手が話し終わった後に「つまり、○○ということですよね」などのフォローを付け足しましょう。
ファシリテーターの補足が適切におこなわれるほど、分かりにくい意見でも参加者全員が情報を理解しやすくなります。
プロセスや責任の所在を明確にし合意を得る
意見が集まり、おおよその方向性が定まってくると結論が明確になってきます。
しかし、結論が明確になったからこそ必要になるのが、今後どのように進めていくのか、責任の所在はどこにあるのかという点です。
具体的なプロセスを明確にすることは、その後の行動や目標を明確にすることにつながります。
また、責任の所在を明確にすることで、当事者意識をもって行動できるため、目標を達成する可能性を高まることができるでしょう。
まとめ
以上、ファシリテーションについて意味や目的、役割や必要なスキルについて詳しく解説してきました。
ファシリテーションは会議などの話し合いをスムーズに進めるために重要な役割を担っており、ビジネスシーンでも注目されています。
また、ファシリテーションスキルは、ビジネススキルの一つとして需要が高まっていくるため、機会があれば積極的にファシリテーターの経験を積んでいくと良いでしょう。
いいね!
この記事をシェアする
この記事を書いた人
すべらないキャリア編集部
「ヒトとITのチカラで働く全ての人を幸せにする」というミッションのもと、前向きに働く、一歩先を目指す、ビジネスパーソンの皆さんに役立つ情報を発信します。