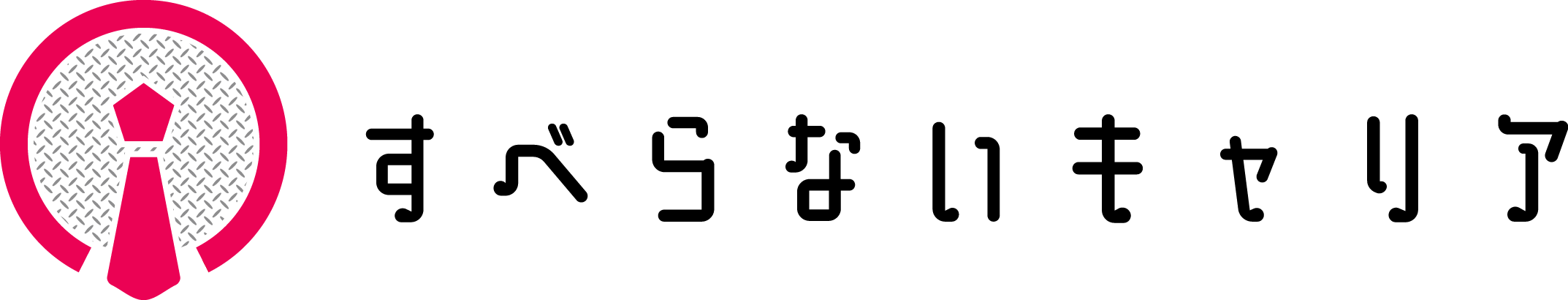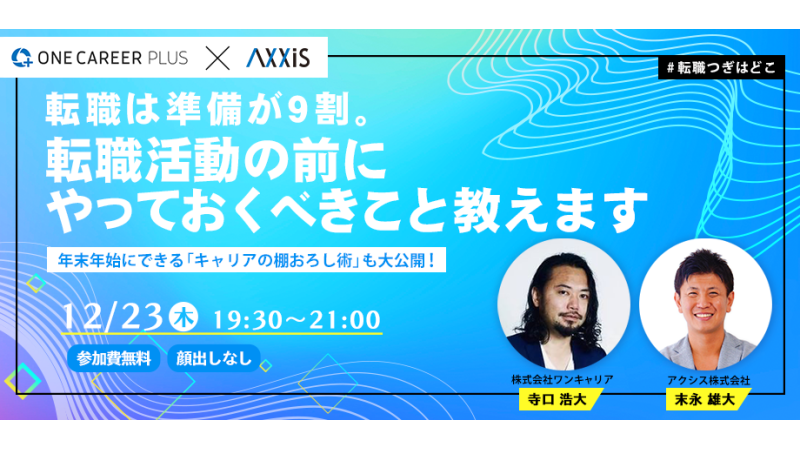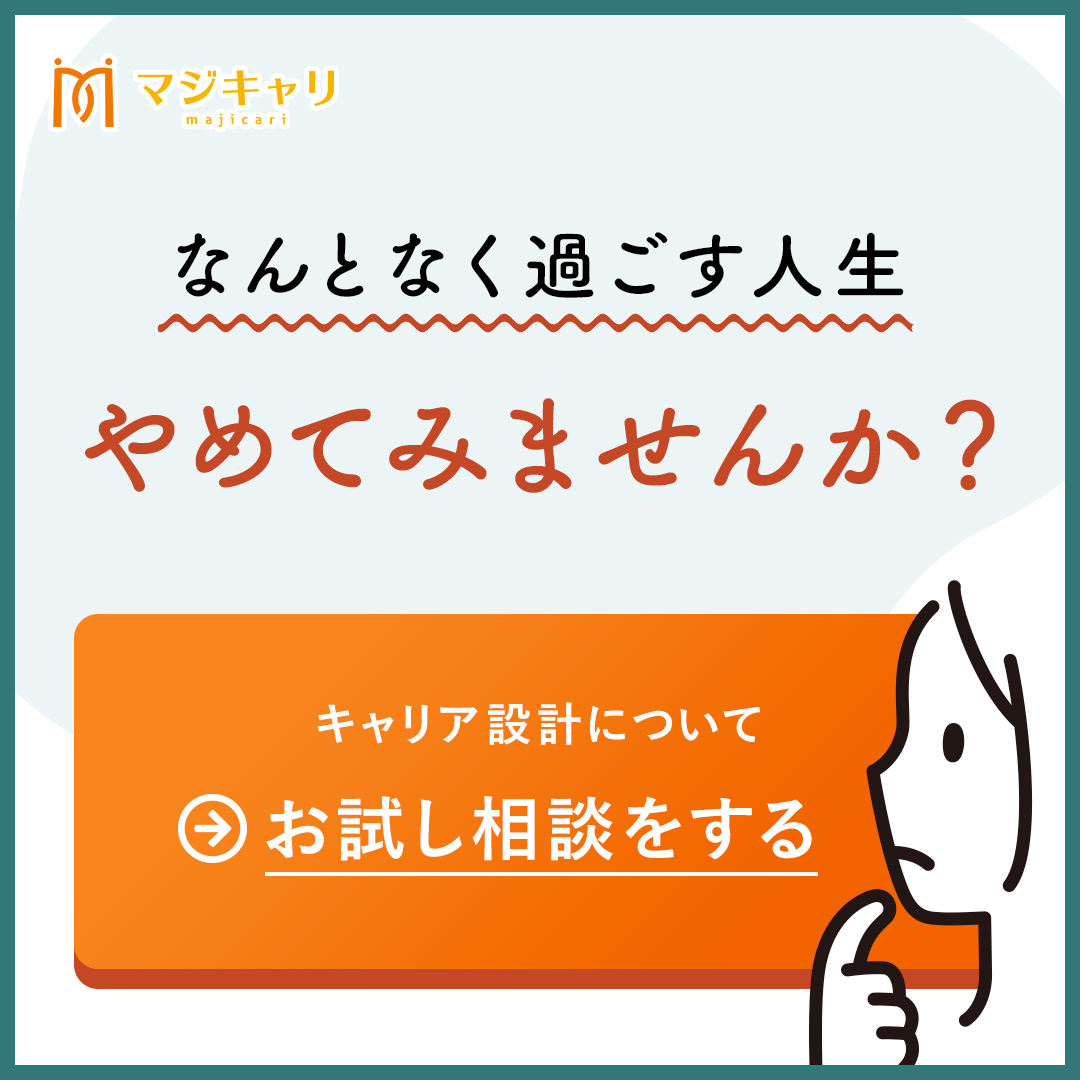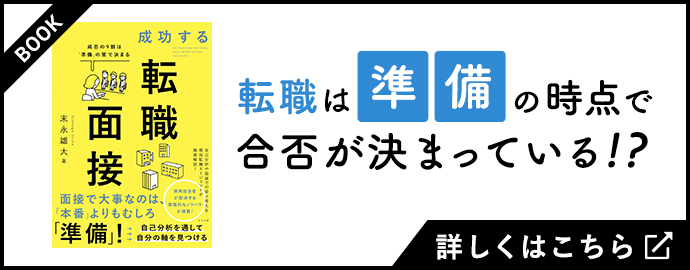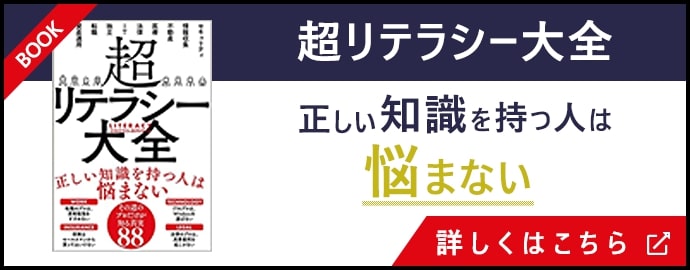目次
企業が効率的に目標の達成をするために必要不可欠なKPIですが、最近では、部署やチーム、個人など幅広いビジネスの場面でも活用されています。
しかし、「KPIの設定するにしても、どのようにすれば良いのだろう」「チームに導入したいけれど上手くやれる自信がない…」と感じる人もいるのではないでしょうか?
そのため、今回はKPIの意味やメリットをはじめとして以下の内容について解説していきます。
- KPIの意味やメリット
- KGI・KSF・OKRとの違い
- 最適なKPIの設定方法や運用のコツ
KPIをしっかりと理解しておくことで、目標達成率を高めたり、さらにより高い目標へチャレンジしたりすることができるようになるでしょう。
KPIとは?
KPIとは、「Key Performance Indicator」の略称で、「重要業績評価指標」と言う意味です。プロセスが適切に実行されているかどうかを測る物差しのことを意味します。
もう少し簡単に言えば、目的(ゴール)を達成するための細かい目標を指します。
例えば、KPIとして設定する場合には、下記のような目標が挙げられるでしょう。
- 1ヶ月の受注件数100件
- クライアントへの訪問件数200件
上記のように、目的に関連する具体的な目標(KPI)を設定することで、達成できれば最終的な目的を実現することができる可能性が高まります。
そのため、最終目的を達成するためには、まずKPIで細かい目標を設定しておくことが大切です。
ここからは、KPIをさらに詳しく理解するため、KPIを設定するメリットやKGI、KSF・OKRとの違いなどについてお伝えしていきます。
KPIを設定するメリット
KPIを設定するメリットは、主に次の4つです。
KPIを設定することで、目標と行動が明確になり、パフォーマンスの向上につながります。
そのため、KPIのメリットをしっかりと理解し、有効に活用できるようにしましょう。
行動が明確になる
KPIを設定する場合には、「1ヶ月で受注件数100件達成」のように、定量的で具体的な目標を設定します。
そのため、行動の計画を立てる際にも、
- 現在の受注率は50%だから、1ヶ月で100件受注するためには200件の訪問が必要
- アポイント率が50%だから、200件の訪問をするためには、400件のアポイントが必要
このように、目標を達成するために必要な具体的な行動の指標を明確にすることができるでしょう。
目標達成に必要な施策を練ることができる
KPIを設定することにより、目標に対する具体的な行動が明確になり、業務の全体像や問題点の把握し、現時点でのチーム・個人の課題なども明確にすることできるため、具体的な施策を練ることができるようになります。
例えば、
- 現在の訪問件数の平均は150件だから、訪問件数を増やすために『新しい営業リストを作ろう』
- 受注率が50%から65%に上がれば、150件程度の訪問件数でも可能性が見えるので『ノウハウの共有をしよう』
上記のように、現在の数値から課題や注力するべき施策を練ることができるようになります。
その結果、目標達成においてボトルネックとなっている点を見つけやすくなり、より目標達成の確率を上げることにもつながるでしょう。
早期の対策や問題解決が可能になる
KPIを設定しておくことで、目標が達成できない時にも行動の方向修正をおこなったり、以下のように問題点を明確にして対策を練ることができるようになります。
- 課題:受注件数が100件達成しない可能性がある
- 原因:受注率が40%と想定よりも低いため訪問件数が足りていない
- 対策:受注率を40%に再設定して、訪問件数の数やテレアポの数を増やす
また、目標を達成できなかった場合でも「受注率」「訪問件数」「アポイント数」など、具体的な行動目標や数値を可視化することができているため、事後検証で原因を探りやすくなるでしょう。
組織全体のパフォーマンスが向上する
KPIを設定して目標や行動を明確にすることで、組織全体のパフォーマンスの向上につながるでしょう。
一般的にKPIは部署やチーム単位で採用されるため、共通のKPIを設定することで、従業員それぞれのやるべきことが明確になります。
また、具体的な目標設定をチーム単位でおこなうことで、チーム全体の課題や個人の課題も明確になり、一人一人がどのような改善をおこなっていけば良いのか判断することも可能です。
その結果、部署やチームでの情報共有や課題解決を効率的におこなうことができるため、チーム全体のパフォーマンスの向上につながるでしょう。
KPIとKGI、KSFとの違いや関係性
「KPI」とよく似た言葉に、「KGI」と「KSF」があります。どちらも目標を達成するための重要な指標となるため、以下でそれぞれの違いをしっかりと理解を深めておきましょう。
KGIとは
KGIとは「Key Goal Indicator」の略称で、「重要目標達成指標」を表します。
簡単にいえば「最終目的(ゴール)」を表す指標のことです。
KPIで設定する指標が「目標」なのであれば、KGIには最終的な「目的」となる数値を設定します。
数値で表せる企業の最終目的の一つとして「売上」が挙げられるでしょう。
例えば、KGIとして「売上1億円を達成する」と設定した場合には、KPIは「売上1億円を達成するために受注件数100件達成する」となります。
KPIはあくまでKGIに沿った目標となるため、KPIを設定する場合には、KGIがどのように設定されているかを意識しておく必要があるでしょう。
つまり、『KGIは最終目的(ゴール)』『KPIは目的を達成するための目標』という点が両者の違いになります。
KSFとは
KSFとは、「Key Success Factor」の略称で、「重要成功要因」とも呼ばれます。
KPIが最終目的(KGI)を達成するための目標なのであれば、KSFはその目標を達成するための「手段」と言い換えることもできます。
KPIには、「受注件数100件獲得」や「資料請求件数を10%増やす」というように、必ず指標となる具体的な数字が当てはまります。
一方、KSFの場合には具体的な数字は用いません。
代わりに、
- 受注件数100件を達成するために「インサイドセールスに切り替える」
- 資料請求件数を10%増やすために「パンフレットの内容を見直す」
このように、抽象的なアクション(手段)がKSFの指標となります。
KGI・KSF・KPIの関係性
3つの指標を順に並べてみると、それぞれの関係性がわかりやすくなります。
- KGI:最終目的(ゴール)
- KSF:最終目的(KGI)を達成するための手段
- KPI:目的達成に必要な手段に基づいた具体的な目標
実際に数値を用いるとこのような感じですね。
- KGI:売上1億円を達成
- KSF:受注件数の増加・訪問件数の増加
- KPI:「1ヶ月の受注件数を100件達成」「訪問件数200件達成」
つまり、KPI、KGI、KSFの3つの指標のうち1つでも欠ければ関係が成立しないということです。
そのため、KPIを設定するときは単独で用いるのではなく、必ずKGIとKSFの設定もおこなう必要があるという点を押さえておきましょう。
KPIとOKRの違い
「KPI」と間違えやすい用語として「OKR」という言葉が存在します。
OKRとは、(Objectives and Key Results)の略称で、達成すべき目標(Objectives)と目標達成のための主要な成果(Key Results)のことを指します。
OKRはKPIと同様に、目標の管理法に関係する内容のため、間違えてしまうことも多いですが、厳密には以下のような違いがあります。
- 目標設定:定性的・定量的
- 目標の共有範囲:全社員
- 目標の達成率:60〜70%でOK
- 評価頻度:1ヶ月〜3ヶ月に1回
OKR:全体の目標達成に必要な個々の目標と成果。
最終目標を達成するためのプロセスを共有する際に用いられる
- 目標設定:定量的
- 目標の共有範囲:チーム・部署単位
- 目標の達成率:100%達成必須
- 評価頻度:1ヶ月に1度 or 適時
KPI:企業の最終目的(KGI)に必要な行動目標。
具体的な行動計画を立てて目的を達成するために必要
上記のように、似た部分があるため勘違いしやすいですが、目的や共有範囲が異なるためポイントを抑えて適切に活用できるようにすると良いでしょう。
最適なKPIを設定するための手順
目標を達成するために最適なKPIを設定するには、次の手順に沿って各指標を決めていきます。
どれだけ高い目標を掲げても、目的に結びつかない目標では意味がありません。そのため、本項で説明する手順に沿い、必ず3種類の指標を設定するようにしましょう。
KGIの設定
目標を立てる場合には、はじめにKGI(最終目的)から先に設定していきます。
KGIを設定する際には、下記のポイントを意識するようにしましょう。
- 最終目的は企業全体の利益につながっているか
- 定量的で数値の計測ができるかどうか
- 目的が達成できるものかどうか
企業全体で設定する場合には、「売上1億円達成」のような数値を設定することもありますが、部署でKGIを設定するときは「営業スタッフのノルマ達成率を90%にする」、個人の場合は「営業時の満足度を20%高める」などケースによって指標が異なってきます。
いずれにせよ、より具体的に数値化でき、達成が可能な範囲のKGIを設定することがポイントになるでしょう。
KSFの設定
KGIが決まったら、今度はおのずとKSFの指標も見えてきます。
たとえば、KGIが「Webサイトの会員数を1万人増やす」指標だとしましょう。
会員数を増やすには、「魅力的なコンテンツを用意する」「広告を出稿する」「サンプル提供により行動喚起につなげる」といったプロセスが想定されます。
上記プロセスの各要素はいずれもKSFとして設定でき、なおかつ数値化してKPIとしても活用できるものになっています。
また、KSFを設定する時には、
- コントロールできる or コントロールしやすいか
- KGIの達成に効果的かどうか
このような指標で判断していくと良いでしょう。
KPIの設定
KGIからKSFをピックアップしたら、今度は具体的な数値に落とし込んでいきます。
先ほどの例をもとに考えていきましょう。
- KSF「魅力的なコンテンツを用意する」→KPI「Web記事を100記事投稿する」
- KSF「広告を出稿する」→KPI「CTR(広告クリック率)を5%に高める」
- KSF「サンプル提供により行動喚起」→KPI「CVR(成約率)を2%に高める」
上記の通り、KSFとして設定した指標は数値化することでKPIとして活用していくことが可能です。
しかし、KPIを設定したからといって必ず目標が達成できるわけではありません。
そのため、目標達成が可能かどうかは、定期的に確認をおこない、課題解決や方向修正をしていきます。
また、目標が達成できなかった際には、必ず数値の検証と問題点の抽出、課題解決のための具体策の提案までおこない、次回のKPIを設定する際に役立てるようにしましょう。
KPIを設定する際のコツ
KPIを設定する場合、適切なKPIが設定できているかどうかは大切です。
しかし、KPIを設定する際に「正しく設定できているのか?」と不安に感じる人もいるでしょう。
そこで、ここからはKPIを設定する際に役に立つコツや注意点について解説していきます。
KPI設定はSMARTに!
KPIを設定するときは、SMARTのフレームワークが有効です。
SMARTとは、以下5つの単語の頭文字から形成された言葉です。
- Specific:具体的な
- Measurable:計測可能な
- Achievable:達成可能な
- Relevant:適切な
- Time-bounded:期限を定めた
上記5つを意識してKPIを設定することで指標がより具体化し、部署やチーム内で共有しやすくなります。
また、今までKGI・KSF・KPIで利用してきた例を用いると下記のように当てはめることも可能です。
- Specific:今年度の売上1億円達成のために受注件数を増やす
- Measurable:1億円達成・毎月100件受注
- Achievable:10件の受注を増やすのは現実的
- Relevant:1億円達成するためには月100件の受注が必要
- Time-bounded:今年度(12ヶ月)・毎月(1ヶ月)
目標:今年度の売上1億円達成のために、受注件数を毎月10件増やして100件/月にする
上記のように、現時点での数値目標をもとに適切な目標か、達成可能かどうかなどの判断をしてくことができるので、活用してみると良いでしょう。
KPIを設定する際の注意点
KPIを設定する際は、次の点に注意してください。
- KPIは一つに絞る
- 定期的に指標を見直して変更する
- KPIは達成可能な範囲で設定する
KPI設定のよくある失敗として、「KPIの数を多く設定しすぎる」「KGIにつながらないKPIを設定してしまう」ということが挙げられるでしょう。
KPIの数を多く設定しすぎることで、行動の優先順位がわかりづらくなったり、行動指標がブレて成果に結びつかない可能性があります。
また、KGIと関連性の薄いKPIを設定した場合には、目標を達成してもKGIの達成につながらない可能性があるため、思い切って指標を変更することも大切です。
そして、「目標は高いほうが良い」と思い、KPIを高く設定してしまった場合、従業員のモチベーションの低下を招く可能性があるため、KPIは達成可能な範囲で設定するようにしましょう。
KPIを上手く運用するためには?
KPIを上手に運用し、目標達成率を高めるためには、以下の点を意識してみてください。
上記のような方法を知っておくと、より効率的にKPIをマネジメントすることができるので、ぜひ活用してみてください。
KPIの設計をシンプルにする
KPIの設計をシンプルにすることで誰が見ても目標がわかりやすくなり、チーム内の混乱を回避できます。
適切な目標設定をする際にはSMARTモデルが活用できますが、シンプルなKPIの設計をおこなう際には、下記のポイントを意識すると良いでしょう。
- 1つの目標に対して、1つの要素だけになっているか
- 誰がみても目標の意図が理解できるか
上記のように、目標に含まれている要素を1つに絞り、誰がみても目標の意図を汲み取れるかどうかは目標設定において重要です。
そのため、設定した目標がシンプルになって理解しやすいかどうかは常に意識していくと良いでしょう。
KPIの評価を明確にする
KPIの評価を明確にすることは、適切にチームの評価をおこなうためにも大切なポイントになります。
また、評価を明確にする際には以下のポイントを意識しましょう。
- 主観ではなく客観的に判断して誰もが同じ評価を下すことができるか
- 評価者や批評家者が納得できる評価基準かどうか
- 評価に対しする具体的な行動が明確になるかどうか
上記のポイントは、人事評価などでも意識するべきポイントで、適切な評価をするためには重要なポイントです。
KPI評価では、一般的には1〜5で評価されるケースもあれば、達成度で0%〜100%のような形で評価されるケースもあります。
しかし、どのように評価をするにしても、「『2』は目標に対する達成率が60%以上」「『3』は目標に対する達成率が100%以上」のように、誰が評価しても間違えがないように明確に設定しておくことが必要でしょう。
KPIに基づく数値目標を設定する
KPIを適切に運用していくためには、KPIに基づく数値目標を設定が必要です。
KPIを設定する際には既に目標数値を明確にしているケースも多いですが、既存の目標数値と関連する行動の数値も細分化して設定していくことで、よりKPIの達成に向けて行動しやすくなります。
例えば、KPIを『1ヶ月の受注件数100件』と設定して場合の数値目標は下記の通りです。
- 『1ヶ月の受注件数100件』→『1ヶ月のアポイント件数200件』
- 『1ヶ月のアポイント件数200件』→『1ヶ月のテレアポ件数1000件』
KPI:『1ヶ月の受注件数100件』
上記の数値は、「受注率50%」「アポイント獲得率が20%」の場合の数値設定ですが、具体的に数値を用いて示していくことで、KPIに基づく行動目標を明確にすることができます。
また、上記のように細分化した数値目標を設定しておくことで、効果測定をする際にも役立てることが可能です。
そのため、KPIの運用の際には、KPIに基づく数値目標の設定も忘れないようにしましょう。
いいね!
この記事をシェアする
この記事を書いた人
すべらないキャリア編集部
「ヒトとITのチカラで働く全ての人を幸せにする」というミッションのもと、前向きに働く、一歩先を目指す、ビジネスパーソンの皆さんに役立つ情報を発信します。