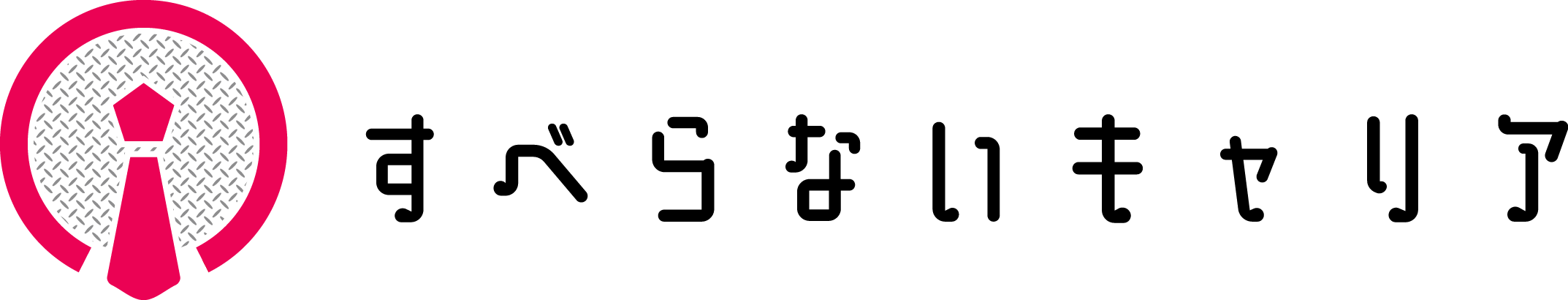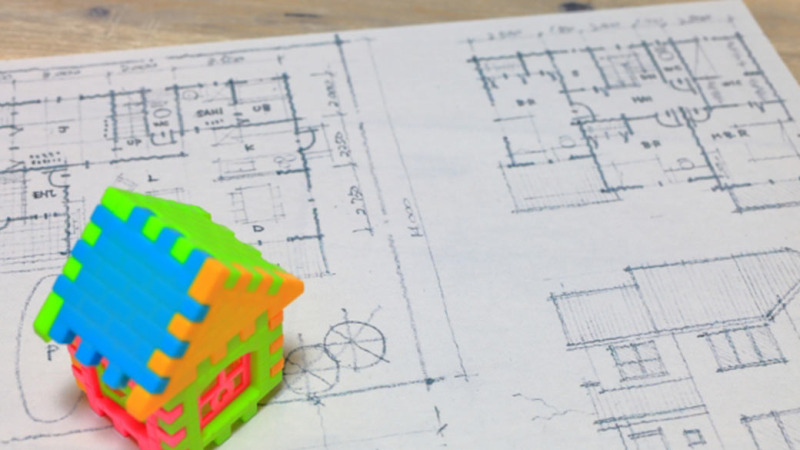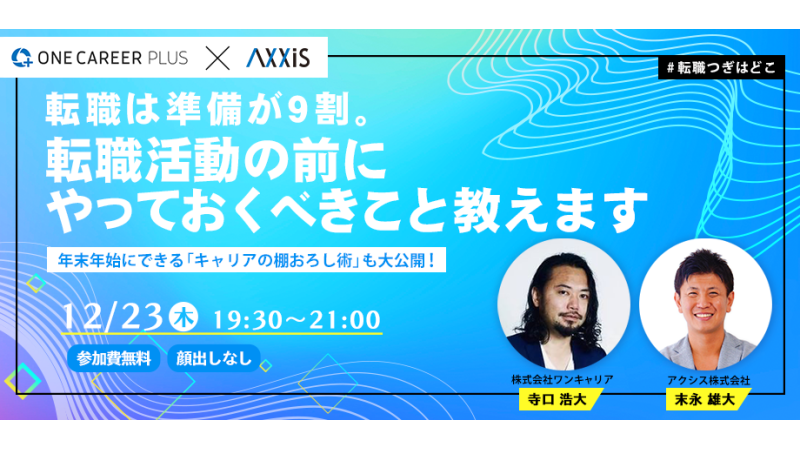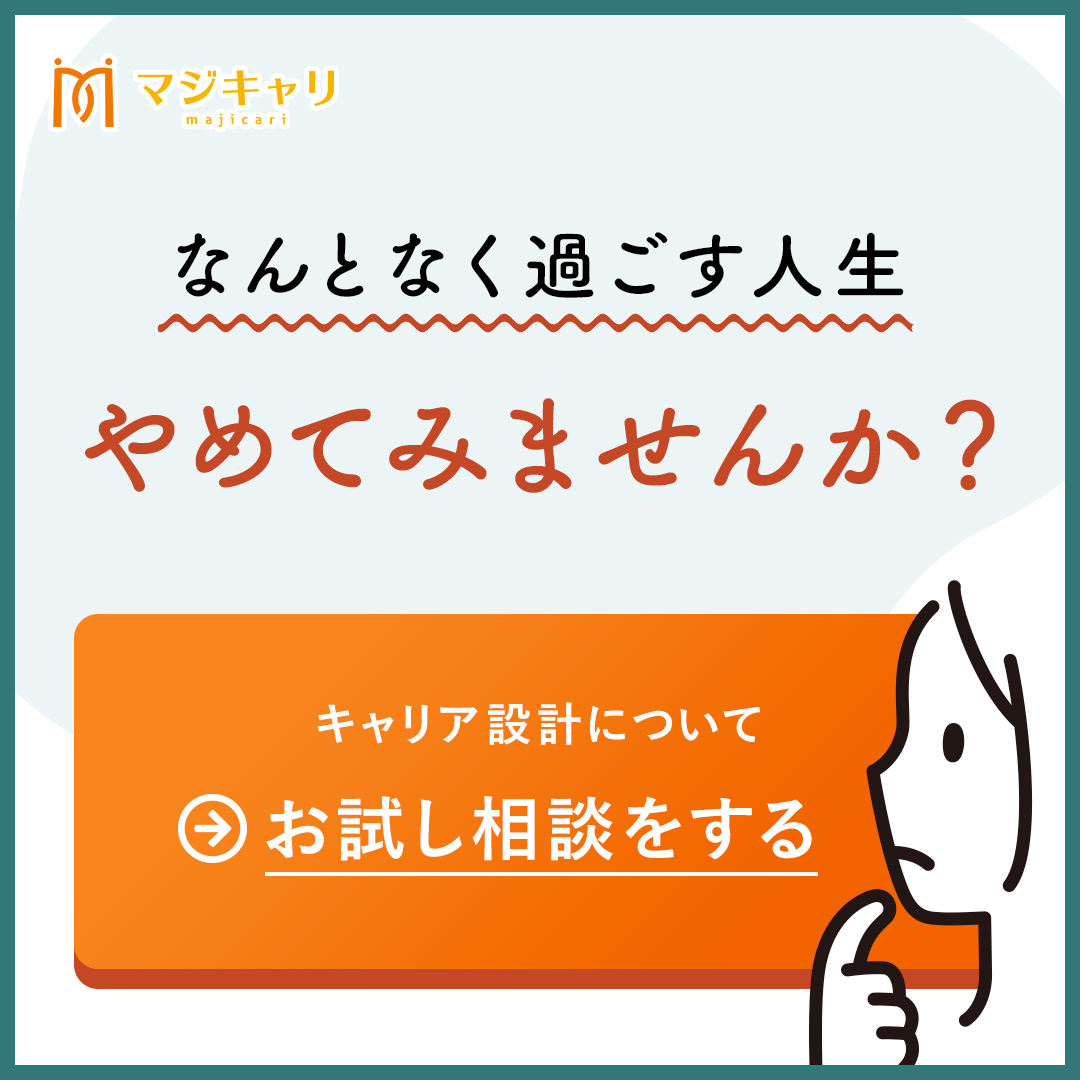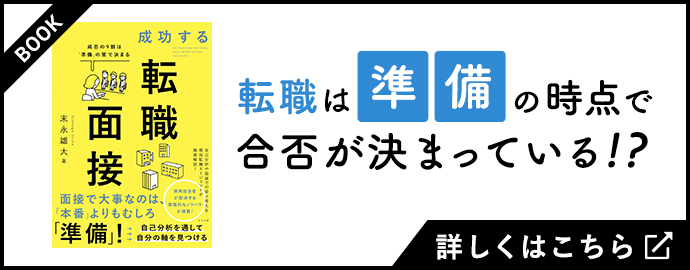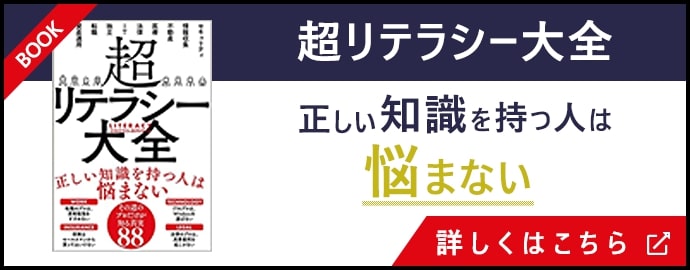目次
建築士とは
子どものなりたい職業ランキングでも度々上位にランクインする常連職業で、年齢問わず人気・知名度の高い職業である建築士。
建築士は建築士法にもとづいて、住宅、マンション、ビルなど、さまざまな建築物の設計や工事の監理をするための国家資格です。
ドラマなどのイメージもあり設計やデザインの仕事がクローズアップされやすいですが、設計内容をもとに建築現場での指揮・監督などを行う業務も含まれます。
建築士と一口にいっても扱える業務範囲の違いにより、1級、2級建築士の2種類に分類され、それぞれに試験・登録制度が異なります。ここからは、1級・2級建築士の違いや建築士の働き方について解説します。
1級・2級建築士の違い
1級建築士と2級建築士の明確な違いは、設計できる建物の規模と構造の制限です。
2級建築士は一般的な戸建て住宅など小規模なものに限られます。
対して1級建築士は2級建築士の取扱範囲である戸建て住宅はもちろん、オフィスビルや学校・病院・公共施設など制限なくどんな建築物でも取り扱うことが可能です。
なお設計できる建築物制限が違うだけで、基本的な仕事内容は変わりません。自身のスキルや関心に合わせて何を得意分野とするのかを決めて業務を行います。
また、建築士免許の発行元も異なります。1級建築士は国土交通省、2級建築士は都道府県がそれぞれ発行元です。
建築士の働き先
建築士は活躍の幅が広い職業です。
建築士の資格を活かせる仕事は、個人の設計事務所を開業するだけではなくゼネコンの設計部門、ハウスメーカー、工務店などもあります。
テレビドラマや映画、ニュースなどの影響から設計事務所で華やかに働くイメージが強いですが、個人開業して活躍出来る建築士は一握りです。多くの建築士はゼネコンやメーカーなどで勤務することとなります。
経験・ノウハウ、クライアントとのやり取り、業界の案件価格相場など現場でしか学べない技術もあります。
独立開業を目指す場合も、まずはゼネコンやメーカーで働きながら現場で技術を習得し、実績を十分に積んだ後に独立を検討する人が多いようです。
どんな働き方をしたいか、どんな目標を持っているのかで働き先を選択しましょう。
建築士の年収
厚生労働省が実施する令和2年賃金構造基本統計調査では、建築士の平均年収は約619万円です。
調査年によっても平均年収は異なりますが、600~650万円ほどといわれています。
国税庁が調査する「平成30年度分民間給与実態統計調査結果」では日本のサラリーマンの平均年収が441万円なので、建築士の年収の高さが分かるでしょう。
また、2級建築士と1級建築士を比較すると、1級建築士の方が扱う建物の制限がない分、年収は高くなります。
建築士は1000万円プレーヤーとして名前が上がる職業です。独立開業した後に多くの指名を受ける人気建築士になれば、1000万円を超える年収を手にする人もいます。
建築士の難易度
建築士になるためには、まずは建築士試験の合格が必要です。
これから受験を目指す方にとっては朗報なのが、建設業界の慢性的な人不足に伴い令和2年度から受験資格が大幅に緩和されました。
要件を満たせば実務経験が無くても受験可能となるため、従来よりも受験ハードルは低くなったといわれています。
とはいえ、建築士試験は専門知識が問われる内容であるので、しっかり対策をしっかり行うのが重要です。ここからは1級・2級のそれぞれで難易度を詳しく解説します。
2級建築士の難易度
過去5年間における建築士試験の合格率は20%前後です。
各年の受験者数、合格者数、合格率はそれぞれ以下の通り推移しています。建築士試験は学科試験と実技(製図)試験の2つからなる試験なので、それぞれ紹介します。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 製図 | 学科 | 製図 | 学科 | 製図 | 総合 | |
| 平成28年 | 20,057人 | 11,159人 | 8,488人 | 5,920人 | 42.3% | 53.1% | 25.4% |
| 平成29年 | 19,649人 | 10,837人 | 7,197人 | 5,763人 | 36.6% | 53.2% | 24.3% |
| 平成30年 | 19,557人 | 10,920人 | 7,366人 | 5,997人 | 37.7% | 54.9% | 25.5% |
| 令和元年 | 19,389人 | 10,884人 | 8,143人 | 5,037人 | 42.0% | 46.3% | 22.2% |
| 令和2年 | 18,258人 | 11,253人 | 7,565人 | 5,979人 | 41.4% | 53.1% | 26.4% |
合格率=難易度ではありませんが1つの目安として考えると、他の国家資格として比較しても合格率は低く、難易度は中~高難易度といえるでしょう。
難易度が高い理由としては、学科試験の合格基準「4科目を13点以上、かつ総得点60点以上」がある点です。
建築士試験は建築・設計に関わる幅広い知識を出題される試験ですが、不得意科目で足きりとなってしまうことのないように、全ての出題科目を満遍なく対策しておくことが重要です。
1級建築士の難易度
直近過去5年間の合格率は以下の通りです。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 製図 | 学科 | 製図 | 学科 | 製図 | 総合 | |
| 平成28年 | 26,096人 | 8,653人 | 4,213人 | 3,673人 | 16.1% | 42.4% | 12.0% |
| 平成29年 | 26,923人 | 8,931人 | 4,946人 | 3,365人 | 18.4% | 37.7% | 10.8% |
| 平成30年 | 25,878人 | 9,251人 | 4,742人 | 3,827人 | 18.3% | 41.4% | 12.5% |
| 令和元年 | 25,132人 | 10,151人 | 5,729人 | 3,571人 | 22.8% | 35.2% | 12.0% |
| 令和2年 | 30,409人 | 11,035人 | 6,295人 | 3,796人 | 20.7% | 34.4% | 10.6% |
実施年によって合格率のバラつきはありますが、合格率は10~12%前後の高難易度試験です。
2級建築士の試験よりも出題範囲が広がるのと、2級と同じ出題科目であってもより詳細に突っ込んだ内容を問う出題となるため、難易度が上がります。
2級建築士を取得済みの人で勉強時間の目安は1000時間程度といわれています。
建築士のやりがい
昔から人気の高い職業である建築士は、どのような点に「やりがい」や「面白さ」を感じるのでしょうか。
1級建築士と2級建築士のそれぞれで実際に建築士として働いている方の意見も参考に紹介します。
1級建築士
学校や病院、レジャー施設など大規模な公共施設や商業施設、モニュメント等の建築物の工事などに携わることができます。
オリンピックや万博など国を上げた一大プロジェクトに参画したり、後世に名を残すような建造物を設計できるのは1級建築士としての醍醐味です。
ただ建物を設計・建築するだけでなく、利用する人々のライフスタイルや働き方を含めてデザインすることができます。
ゼロから建築物を作り上げる達成感や感動は格別です。また、国内だけに留まらず世界に股をかけて仕事をしたい人にも向いています。
2級建築士
2級建築士は戸建て住宅をメインを実施するので、各家庭の生活状況に寄り添った仕事をします。
お客様の希望や理想像を細かくヒアリングしながら、お客様と一緒に具体化するプロセスが面白さの1つです。
不特定多数の人が利用する大規模建築と違って個人宅の設計・建築に携わるので、完成後にお客様が喜んで使ってくれる様子を直に目にすることができる点もやりがいに繋がるでしょう。
また、何十年にも渡って自分の作り出した建築物が残り続けるのもやりがいの1つです。長期間お客様の暮らしを支え、数々のライフイベントを共にする住居を設計出来ることにやりがいを感じる建築士も多いようです。
建築士を目指すなら通信・通学講座の利用が効果的
建築士を目指すのであれば、最初のハードルである建築士試験の合格は避けて通れません。
独学でも合格が狙える試験ではありますが、独学では不安、効率的に勉強を進めたいという人は通信・通学講座を利用するのがおすすめです。
よく出題される範囲をピンポイントに対策できるので効率的に勉強を進められます。
また、建築士試験は年1回しか受験の資格がないため、確実に合格を狙いたい人にも向いています。
通信・通学講座を利用する場合も、受講期間・受講料金・受講方法など、利用サービス、プランによって受講内容が異なります。利用予定サービスのHPを確認するのはもちろん、予算感や口コミなども参考に自分に合った講座を選択しましょう。
まとめ
建築士はただ建物を設計・建築する職業ではなく、建物を利用する人のライフスタイルや働き方を含めてデザインする魅力にあふれた職業です。
高い専門性を求められる職業ではありますが、建築士を目指したきっかけや、この記事で紹介したやりがい・醍醐味などを思い浮かべながら勉強を進めましょう。
いいね!
この記事をシェアする
この記事を書いた人
すべらないキャリア編集部
「ヒトとITのチカラで働く全ての人を幸せにする」というミッションのもと、前向きに働く、一歩先を目指す、ビジネスパーソンの皆さんに役立つ情報を発信します。